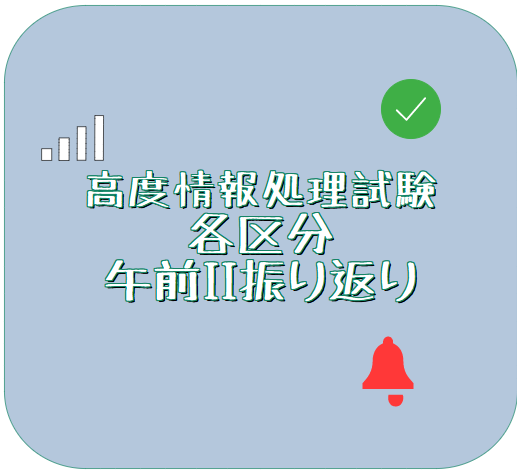
情報処理試験、受験された方、お疲れ様でした。
試験が終了して少し時間が経過しましたが、合否発表にはまだ時間があります。
各区分の午前IIの出題分野を分析して本記事でまとめてみました。
この記事をみていただければ、
各区分の午前IIの傾向や全区分を通して見えてくる試験センターの関心の高い分野が見えてくると思います。
振り返りに活用ください。
IPAとしては、出題区分はテクニカル系・ストラテジ系・マネジメント系に分けられるということを公開しています。

試験要綱ver4_7.pdf (ipa.go.jp)
各試験区分の午前II出題割合
1. ITストラテジスト(ST)
| 問題 | 区分 | 問題数 | 割合 |
| 問1~15,17,18,22 | ST | 18 | 72% |
| 問16,19,21 | SA | 3 | 12% |
| 問23,24 | SC | 2 | 8% |
| 問20 | PM | 1 | 4% |
| 問25 | NW | 1 | 4% |
自区分(ITストラテジスト)の出題数は18問で全体の72%に上る。
決定木分析(問3)やSECIモデル(問13)に関する頻出問題が今回も登場していた。
次に多いのがSA(システムアーキテクト)で3問・12%。
STの戦略に基づいてSAが開発するのでノウハウは知っておくべき、ということと思われる。
だが単に合格狙いならば自区分を完璧に仕上げれば合格ラインを超えるので十分である。
2. システムアーキテクト(SA)
| 問題 | 区分 | 問題数 | 割合 |
| 問1~3,5~12 | SA | 11 | 44% |
| 問16~20 | SC | 5 | 20% |
| 問4,14 | ES | 2 | 8% |
| 問13,15 | ST | 2 | 8% |
| 問21,23 | 応用情報 | 2 | 8% |
| 問22,24 | DB | 2 | 8% |
| 問25 | NW | 1 | 4% |
自区分(システムアーキテクト)の出題数は11問・全体の44%で、自区分比率は他の区分の試験と比較して最も少ない。
GoFデザインパターン(問2)や修正(テーラリング)プロセス(問12)に関する出題が頻出傾向のようだ。
POSA(問3)やeシール(問16)は今回が初出題だったと思われる。
SAの次に多いのがSC(情報処理安全確保支援士)。
3. ネットワークスペシャリスト
| 問題 | 区分 | 問題数 | 割合 |
| 問1~15,19 | NW | 16 | 64% |
| 問16~18,20,21 | SC | 5 | 20% |
| 問22~24 | 応用情報 | 3 | 12% |
| 問25 | SA | 1 | 4% |
自区分(ネットワークスペシャリスト)の出題数は16問・全体の64%で多め。
自区分はあまり目新しい出題はなく、問題の内容も古くからあるTCP/IPのプロトコルからの出題が多かった印象。
次に多いのがSC(情報処理安全確保支援士)で5問・20%。
ネットワークとセキュリティは密接な関わりがある(脅威とは、攻撃や侵入の "経路" が大きな意味を持つ)ためである。
4. ITサービスマネージャ
| 問題 | 区分 | 問題数 | 割合 |
| 問1~9,11~13 | SM | 12 | 48% |
| 問10,18~20 | PM | 4 | 16% |
| 問15~17 | SC | 3 | 12% |
| 問14,25 | AU | 2 | 8% |
| 問21 | ES | 1 | 4% |
| 問22 | 応用情報 | 1 | 4% |
| 問23 | DB | 1 | 4% |
| 問24 | NW | 1 | 4% |
他区分からの出題数が最もバリエーションが多かった。
ITサービスマネージャは保守や運用を生業とするので、他区分の知識も幅広く求められるということか。
Redmineを回答させる問題(問12)など、OSSの具体的なソフトウェアを問う問題も、最近の傾向として新しい印象。
5. 情報処理安全確保支援士
| 問題 | 区分 | 問題数 | 割合 |
| 問1~17 | SC | 17 | 68% |
| 問18~20 | NW | 3 | 12% |
| 問21 | DB | 1 | 4% |
| 問22 | 応用情報 | 1 | 4% |
| 問24 | SM | 1 | 4% |
| 問23 | SA | 1 | 4% |
| 問25 | AU | 1 | 4% |
自区分(情報処理安全確保支援士)の出題数は17問・全体の68%。
合格対策としては、ほぼ自区分の勉強だけで十分。
他区分から見ると、SC区分の問題が流用されていることが多いことが分かる。
たとえば、サイドチャネル攻撃(問3。NWの問17と同じ)、サイバーセキュリティ経営ガイドライン(問9。SMの問17と同じ)などだ。
複数の高度試験の合格を目標としている方は、まずはSC合格から狙って経験を積んでいくのが、効果的な取り組み方だと思われる。
総合分析
全区分を通して分析すると、試験センターの関心が高いことが伺われるキーワードが見えてくる。
テーラリングプロセス(SAの問12、SCの問13)やCRYPTREC(STの問23、SAの問19、SCの問10)などだ。
これらは区分をまたいで出題されているためだ。
またISMAP(STの問24、SMの問16)やサイバーセキュリティ経営ガイドライン(SMの問17、SCの問9)は、試験センターであるIPAが元締めであったり積極的に関わっていたりすることもあるので、頻出されていると考えられる。
今後の技術としての期待が根強い量子技術(NWの問22、SCの問6)も横断的に問われている。
またフールプルーフ(NWの問24、SCの問22)やサイドチャネル攻撃(NWの問17、SCの問3)など古くから頻出している問題もあるので、合格だけを考えれば、地道に過去問を解いて対策するのが最も効率的だろう。
おわりに
いかがだったでしょうか?
午前II分析は本ブログにおいて2回目の記事でした。
秋試験向けの分析も行っているので、合わせて覗いてみてください。
本ブログでは、高度情報処理試験の、合格に向けたサポート記事を充実していきます。
「読者になる」ボタンで、ブログの更新時に通知されますので、ご検討ください。
試験センターの合格発表までまだ時間があるので、今後も分析記事を投稿したいと考えています。
ではそれまで。








