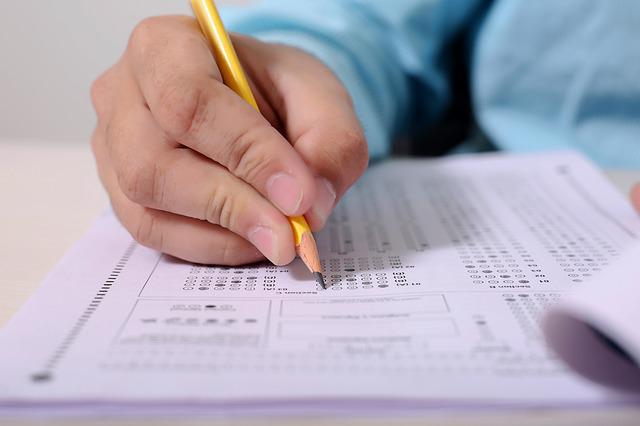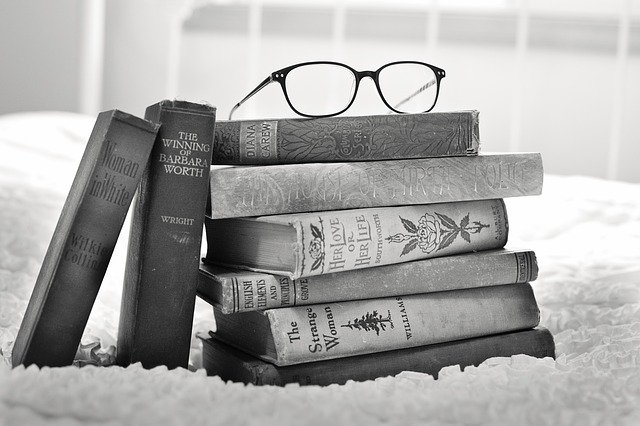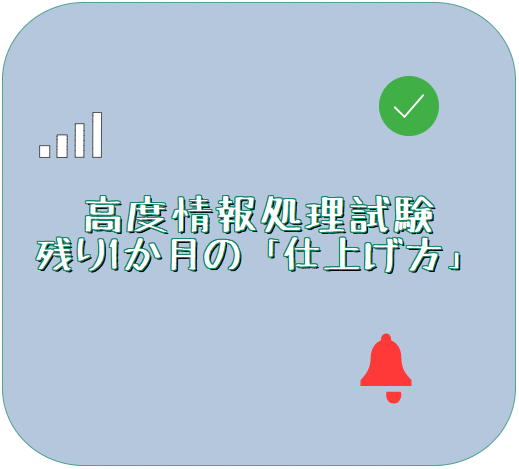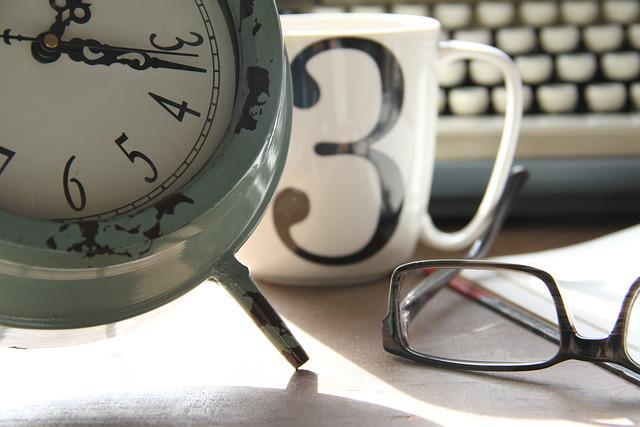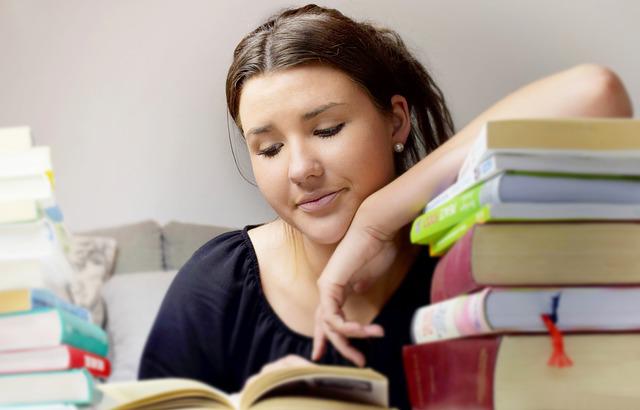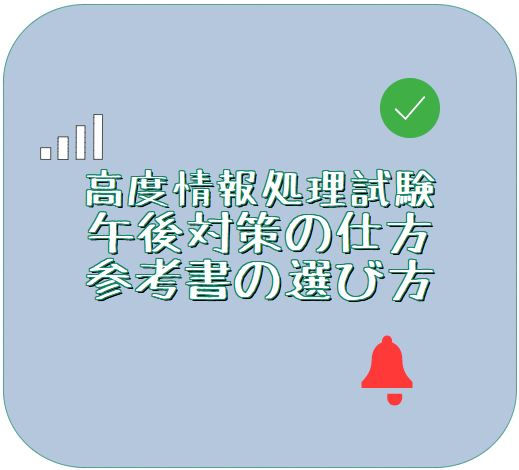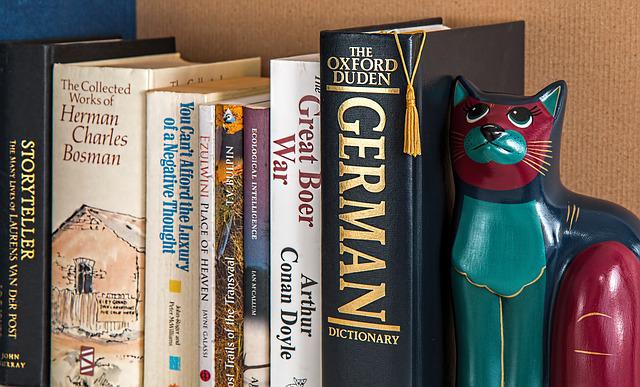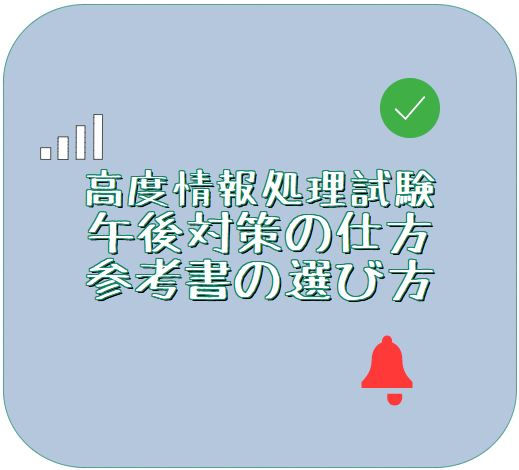
更新:2024/2/18
寒い日が続きますね。
今年は秋の試験は実施日が4月21日と公表されています。
本記事は、高度情報処理試験を受験予定の方を対象に書いています。
次回受ける予定でなかったとしても、意味のある情報を届けたいと思います。
基本情報処理試験と違って、
「高度は何を対策すればいいんだろう?」と悩んでいたり、
「論文や記述式ってどう対策したら?」と思っていませんか。
本記事では、高度情報処理試験を初めて受験される方向けに、
- 高度試験って、基本情報にない何か特別な対策をする必要ある?
- 午後対策で、何を一番重視して進めていけばいい?
- 午後の、記述式と論文って、どう対策分けすればいいの?
- おすすめの参考書は?
といった疑問にお答えしたいと思います。
筆者は高度情報処理試験を全て制覇しております。
実際の体験も踏まえながら、高度に特有の試験対策を説明したいと思いますので、参考にしてください。
1. 基本情報にない特別な対策

基本情報処理試験の受験経験がある方向けに、
まずは高度情報処理試験の対策として同じ所と違う所を
整理して説明します。
1-1. 基本情報と同じ対策でいいところ
高度区分の試験は、午前Iと午前IIは4択マークシート式ですが、
基本情報の午前と同じマークシート選択式です。
これにより、マークシート選択式の特有の対策は、基本情報と同じでよいと言えます。
基本情報でもそうですが、過去問から同じ問題・類題が
多く出題されます。
これにより、特に午前対策としては、過去問を繰り返し解いて対策とする、
ことも同じ所と思います。
1-2. 基本情報とは異なる対策がいるところ
一方基本情報と大きく異なるのは、午後と思います。
まずは、試験時間をチェックしましょう。

基本情報に比べ、長い。体力も必要。
午後I(90分)は、高度試験の全区分で記述式で出題されます。
一方、午後II(120分)は、区分によって記述式か論文かで分かれます。
このため、基本と最も異なる対策が必要となるのは午後です。
ご自身の受験予定の区分を確認し、特に論文が必須の場合は、
基本とは大きく異なる対策がいるでしょう。
記述式は基本情報の午後で出題されている形式ではありますが、
午後IIは120分で長文に取り組む必要があり、
勝手が違うと感じる方も多いのではないでしょうか。
2. 午前対策よりも午後対策に注力しよう

前述の通り、午後の方が過去問一辺倒では対策がしづらく、
勉強の進め方としては午後対策に注力するのがよいでしょう。
逆に午前は過去問からの採用率が高いので、3~4年程度の
過去問を頭に入れておくだけで十分合格できるでしょう。
短絡的な考え方かもしれませんが、合格だけを目的に考えるなら、
出題された単語や意味などを覚えなくても、
問題文と回答のセットだけを覚えれば十分です。
午前はそのように対応をすればよいので、
午後対策をどのように進めるか、が合格への鍵になります。
2-1. 午後対策をどのように進めるか
誤解のないように最初に述べておくと、
その区分に求められている知識、という意味では、
午後であろうと午前であろうと共通しています。
プロマネの例で言うと、PMBOKの基本的な知識エリアや、
ウォーターフォール開発モデルの各工程(V字モデル)は、
午前II(選択式)であろうと午後I(記述式)であろうと
午後(論文)であろうと、求められる知識です。
(午前Iは各区分共通の問題が出題されるので、
その区分特有の知識が求められる比重は小さい)
「その区分に求められる知識」というのが存在することを
念頭に置いたうえで、選択式・記述式・論文それぞれに
対処するイメージで対策するとよいでしょう。
それでは次に、午後対策の話を中心に掘り下げていきます。
3. 午後対策(記述式と論文)

3-1. 記述式の対策
記述式の問題は、時間との戦いになりがちです。
区分によっては、90分の記述式(午後I)と
120分の記述式(午後II)が連続に取り組まなければなりません。
合格点に満たない時の大きな「課題」としては
- 時間が足りない
- 知識が足りない
- 解き方が分からない
のいずれかだと思います。順にみていきましょう。
3-1-1. 「時間が足りない」への対策
これは時間さえあれば合格点に達成できたのに、という
場合の対策です。
この課題への対策は、
長文である問題文の読み方、設問文との対照付けなど、
問題を把握するスピードをあげること
と、
記述する内容のあたりをつけてから制限字数にまとめて
記述するスピードをあげること
の2つが主に考えられます。
前者は、試験区分によって若干クセがあり、
その試験特有の出題のルールのようなものを
理解する必要があります。
たとえば、ITストラテジストでは、
「課題」-「機能」ー「設問」
がセットになっており、「設問」に対応する
「機能」と「課題」が問題文中のどこに記載されているかを
見極めることが重要になります。
これにより、問題に取り組むスピードを向上できます。
後者は、内容のあたりのつけ方と、
あたりをつけたあとに手早くまとめる力が必要です。
この対策は色々あるので本記事だけではとてもまとめられないですが、
最も効果的なものを1つだけ述べておきます。
それは、「迷ったときのルールを予め決めておくこと」です。
区分にもよりますが、たとえば、次のようなルールが考えられます。
問題文から、回答文として記述する情報元が複数あり、文字数的にどちらかを選択する必要がある場合。設問文のキーワードが書かれている問題文中の箇所からの距離が物理的に(問題文の紙面的に)近い方を選択する。
上記のルールを作る場合、「なぜ?」という理由付けは何でも構いません。
重要なことは、時間をかけても意味のないこと(迷う行為)を
減らすということです。
この節については情報量が多かったので、いったんまとめておきます。
■「時間が足りない」への対策■
1. 問題文を把握するスピードをあげること [INPUT SPEED UP]
その試験特有のクセを理解し、把握に努める。
設問文と問題文の関係と構造把握がカギとなる。
2. 制限字数にまとめるスピードをあげること [OUTPUT SPEED UP]
迷ったときに拠り所にする自分だけの記述ルールを
予め決めておく。
3-1-2. 「知識が足りない」への対策
これは前節の前提になっており、時間があったとしても
解けないという場合の対策となります。
「知識が足りない」のは勉強したてであれば仕方のないことです。
「知識が足りない」への対策は、すなわち
「その区分に求められる知識」を習得するということが
対策となるので、当ブログの各試験区分の
対策を覗いてみてください。
ひとつ言えるのは、午前対策のように、過去問のみで
仕上げるのは難しいです。
ここは参考書に頼りましょう。
問題は、ある程度勉強していたり、何度か不合格を経験していたりで、
得点が取れないのが、「知識が足りない」からなのか、
他に理由があるのかが曖昧になってしまう場合です。
ここでは、「知識は足りているが解けない」とは
どのようなパターンがあるか述べておきましょう。
■知識は足りているが解けないとは■
・ある程度自信をもって記述した自分の解答文が、微妙に/明らかに正答文と異なる
・複数の解答候補は思いつくが、最終的に正答となる候補を選択できない
・何度やっても、同じようなミスをする
・参考書を読んでも、納得がいかない
上記のようなケースにあてはまる場合は、
知識というよりも、次に述べる「解き方が分からない」
状況にあると考えられます。
3-1-3. 「解き方が分からない」への対策
これは知識は足りているけど、間違えてしまうという
場合の対策です。
筆者の周囲を見ると、現役やベテランエンジニアのように、
ある程度の知識や経験を備えている方が、
頭を情報処理試験のために切り替えられずに
陥っているケースがあるようです。
そのことの是非はともかく、合格を目指すならば、
いったんは自分の自信も経験も置いておいて、
解き方がわかってないかも? と自分の思考回路を
振り返ってみてください。
この節で言いたいことは、自分の考え方のクセを、
情報処理試験合格のために、矯正することにあります。
このことを理解するには、いちど情報処理試験に臨んだり、
過去問を実際に解いてみる必要があります。
その上で、自分の疑問を言語化して、
さらにその上で、なぜその考え方ではいけないか、を
納得しなおす必要があります。
このプロセスには、一定の勉強時間がかかります。
もしも試験が直前に迫っているのならば、
考え方は納得しなくてもよいので、
正答の表現や参考書に書かれていることを、
「鵜呑み」してしまいましょう。
(あるいは、単にその問題を捨てるか)
この節に書かれていたことをまとめておきます。
■「解き方が分からない」への対策■
「自分の考え方のクセ」を客観視し、試験合格のために考え方を矯正する。
実際に問題を解いてみて、自分の考え方のクセを認識したら、
その思考プロセスを言語化し、なぜそのプロセスだといけないのかを
納得する。
時間が無ければ、参考書に書かれていることを、「鵜呑み」する。
単に捨てるのも手。
こうした、"セルフアジャスト" のプロセスは、
試験合格に限らず、さまざまな人間関係の場面でも、
重要なことだと思います。
3-2. 論文の対策
論文は、人によっては問答無用で苦手意識を持っており、
この時点で受験者にとって大きな差になるところと思います。
筆者も初の論文試験はとても警戒・勉強しても身になった感覚を持てず、
何度か不合格になり苦手意識を持っていました。
ただ、論文も書き方やコツがあります。
ひとたび、合格した区分があったあとは、基本的には、
私はむしろ論文系の試験区分の方が対策が立てやすい、と
思っています。
このコツのようなものを一言で言い表すのは難しいですが、
それでもあえて言うと、
「求められている"論文構造"に気付くこと」
だと思っています。
また、単に知識・経験が足りなくて論文が書けない、
ということもあります。
120分という時間をどうやって使うか、という点も、
実際に取り組んでみないと、自分に最適な
時間配分は導き出せないと思います。
こうした、「その区分に求められる知識」や、
論文に対する基本的なお作法などは、参考書に頼りましょう。
また、論文対策においては、最終的に、
自分の表現に"昇華"させる必要があります。
このために参考にしていただきたい本ブログのオリジナルのフレームワークが、
「論文事例マップ」です。
別記事にまとめていますので、合わせてご参考ください。
■論文事例マップの作り方■
上記のリンクは、
「求められている"論文構造"に気付くこと」
を自分の論述につなげる試みでもあります。
コツのようなものを会得する一助になれば幸いです。
4. おすすめの参考書
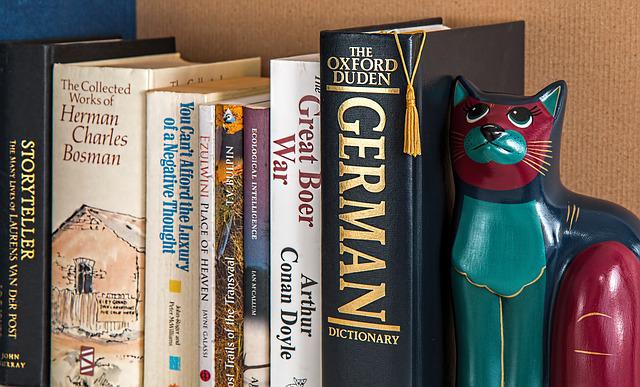
色々述べましたが、ここからは、午後対策となる、
記述式と論文の参考書を筆者の体験をもとに紹介していきます。
4-1. 記述式対策の参考書
記述対策に求めるポイントは、次の1点です。
解説が充実していること
どの区分にしろ、勉強し初めから試験センターの定義する
「正解」を記述する事はできないでしょう。
自分の考え方のクセを意識して、「正解」に合わせる行為が必要です。
そこで必要なものが、「解説の充実度」です。
ここからは、私自身の体験も踏まえて、参考書について評価してみましょう。
iTEC 重点対策
一昨年、ITストラテジストに合格した筆者は、
記述対策にiTECの『重点対策』を用意しました。
リンク
午前II、午後I、午後IIまですべて
これ1冊でカバーしているところが強みです。
紙面の配分も同等か、しいて言うならば
午後II対策の分量が少ないと言えるかもしれません。
記述式の対策は解説が充実していることが重要なので、
その観点で評価してみますと、
- 200ページ超の分量
- 段階的に仕上げることができる仕組み
(テクニック、作成例、実践、解説と節立てされている)
- とりあげている過去問(解説)16問(うち3問が組込みシステム)
と、かなり充実していると言えそうです。(2020年版の評価です)
ただ、解説自体に納得がいかないものも一部でありました。
たとえば、解説文が、問題文の引用や焼き直しに終始しており、
「なぜその回答になるのか?」という論理が足りないと感じるものがありました。
その正答ならば、問題文のこの部分を引用しないのはなぜ?
といったような疑問がわくものもありました。
ただし、筆者の場合は一発で合格できたので、
上に指摘した問題点も大した問題ではないのかもしれません。
翔泳社 情報処理教科書
前々回合格できたシステム監査技術者の際は、
翔泳社の『情報処理教科書』で準備しました。
最新版ではなく、2014年版を中古で購入しました。
リンク
比較的、午後対策に特化しています。
全体的な章立てとしては、
などいくつかの体系に分けられており、
章ごとに知識・午後I対策・午後II対策ができるようになっています。
章の体系からして、合格に向けた対策がとれることと同時に、
各監査のフェーズにおける専門知識を習得できるようになっており、
実際の監査業務に役立てやすい構成になっていると感じます。
特に、第1章に書かれている「監査とは」の部分は個人的に必見です。
なぜ監査が必要か、監査はどうあるべきで、
実務を踏まえてどうアジャストする必要があるかなどといった
観点が含まれています。
実体験を通じておぼろげながら理解できているという人でも、
よりクリアに理解しなおすことができます。
なお、筆者は2014年版で対策し2020年に受験しましたが、
試験体系も、ましてや監査の勘所といった点は
あまり変わりません。
(何しろ監査という概念そのものは、ITが登場する前からあったので)
ですので、対策本を検討する際は、
最新のものに固執せず、中古で安く仕入れるという
考え方もアリだと思います。
4-2. 論文対策の参考書
本記事では1冊、参考書のシリーズを紹介します。
リンク
論文のある試験区分では『合格論文の書き方・事例集』という
シリーズが出ており、その名の通り、論文を書く上での
言い回しや論旨展開の事例集として活用できます。
筆者の場合、基本的に論文系の試験区分の試験対策には
このシリーズで準備しています。
とにかく、文の事例が豊富。
おすすめする点は、これにつきます。
論文で、どのように表現するべきか迷ったとき、
事例が豊富にあると、参考にしたり取捨選択して
自分のものにできたりします。
おわりに
いかがだったでしょうか?
高度情報処理試験を受験予定で、どのように対策を
進めればよいか、考え方の一助となれば幸いです。
今回の春試験のスタートダッシュ記事も参考に載せました。
どのように勉強のモチベーションをあげればよいか、
IPA公開の統計情報も元に紹介しているので、
よければ合わせてご覧ください。
studyrolerole.hatenablog.jp
本ブログでは、高度情報処理試験の、合格に向けたサポート記事を充実していきます。
「読者になる」ボタンで、ブログの更新時に通知されますので、ご検討ください。
それでは、ともに頑張りましょう。
ではそれまで。